再発性多発性硬化症の再発抑制、tolebrutinib vs.teriflunomide/NEJM

再発性多発性硬化症の患者において、tolebrutinibは年間再発率の低下に関してteriflunomideに対して優越性は示されなかった。カナダ・トロント大学のJiwon Oh氏らTolebrutinib Phase 3 GEMINI 1 and 2 Trial Groupが、2つの第III相二重盲検ダブルダミーイベント主導型試験「GEMINI 1試験」と「GEMINI 2試験」の結果を報告した。tolebrutinibは中枢移行性の高い経口ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)阻害薬で、末梢性炎症および疾患関連のミクログリアおよびB細胞を含む中枢神経系の持続的な免疫活性を調節する。再発性多発性硬化症の治療における有効性および安全性の、さらなるデータが求められていた。NEJM誌オンライン版2025年4月8日号掲載の報告。
GEMINI 1試験、GEMINI 2試験で、年間再発率を評価
GEMINI 1試験は24ヵ国162施設で、GEMINI 2試験は25ヵ国155施設で参加者のスクリーニングを行った。McDonald診断基準2017により再発性多発性硬化症と診断され、総合障害度評価尺度(EDSS)スコア(範囲:0~10、高スコアほど障害進行を示す)が5.5以下、再発が過去1年以内に1回以上、過去2年以内に2回以上あったか、過去1年以内にT1強調MRIで検出されたガドリニウム増強脳病変が1つ以上あった18~55歳の患者を適格とした。適格患者は、tolebrutinib 60mgを1日1回、食事とともに経口投与する群、またはteriflunomide 14mgを1日1回、食事とともに経口投与する群に1対1の割合で無作為に割り付けられた。各参加者には1日2錠が投与され、うち1錠は外見がtolebrutinibまたはteriflunomideと同一のプラセボが投与された。
主要エンドポイントは年間再発率であった。重要な副次エンドポイントは6ヵ月以上持続する障害進行で、2試験全体におけるtime-to-event解析で評価した。
年間再発率の率比、GEMINI 1試験1.06(p=0.67)、GEMINI 2試験1.00(p=0.98)
2020年6月25日~2022年8月8日に、GEMINI 1試験では974例(tolebrutinib群486例、teriflunomide群488例)が無作為化され、GEMINI 2試験では899例(447例と452例)が無作為化された。試験を完了したのは、GEMINI 1試験のtolebrutinib群84.2%、teriflunomide群85.0%、GEMINI 2試験はそれぞれ85.9%、83.6%で、追跡期間中央値は139週間であった。
両試験・両治療群の被験者特性は類似しており、GEMINI 1試験では、平均年齢はtolebrutinib群36.8±9.0歳、teriflunomide群36.6±9.4歳、女性被験者割合はそれぞれ68.7%と66.6%、EDSSスコアは両群ともに2.4±1.2、診断後期間は4.8±6.2年と4.6±6.0年などであった。
tolebrutinib群とteriflunomide群の年間再発率は、GEMINI 1試験では0.13と0.12(率比:1.06、95%信頼区間[CI]:0.81~1.39、p=0.67)、GEMINI 2試験では0.11と0.11(1.00、0.75~1.32、p=0.98)であった。
6ヵ月以上持続する障害進行を有した被験者の割合(2試験のプール解析)は、tolebrutinib群8.3%、teriflunomide群11.3%であった(ハザード比:0.71、95%CI:0.53~0.95、事前規定の階層的検証計画により正式な仮説検証は行われず、信頼区間の幅は多重検定に関して補正されていない)。
有害事象が発現した被験者割合は両治療群で類似していたが、軽度の出血が、tolebrutinib群のほうがteriflunomide群よりも高率であった(点状出血4.5%vs.0.3%、過多月経2.6%vs.1.0%)。
(ケアネット)
関連記事

ビタミンD補充、多発性硬化症の疾患活動性を抑制するか/JAMA
ジャーナル四天王(2025/03/27)

再発性多発性硬化症、抗CD40L抗体frexalimabが有望/NEJM
ジャーナル四天王(2024/03/01)
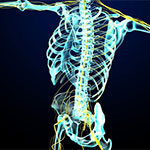
再発性多発性硬化症の再発率をublituximabが低減/NEJM
ジャーナル四天王(2022/09/05)
[ 最新ニュース ]

慢性C型肝炎、ソホスブビル/ダクラタスビルvs.ソホスブビル/ベルパタスビル/Lancet(2025/05/16)
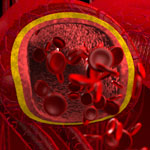
obicetrapib/エゼチミブ配合剤、LDL-コレステロール低下に有効/Lancet(2025/05/16)

死亡リスクの高いPAH患者に対するアクチビンシグナル伝達阻害剤sotatercept上乗せの有効性が証明された(解説:原田和昌氏)(2025/05/16)

アトピー性皮膚炎への新規外用薬、既存薬と比較~メタ解析(2025/05/16)

CT検査による将来のがんリスク、飲酒や過体重と同程度?(2025/05/16)

アリピプラゾール持続性注射剤の治療継続に影響する要因(2025/05/16)

“スマートシャツ”で心臓病を予測(2025/05/16)

子宮頸がんワクチンの接種率は近隣の社会経済状況や地理に関連か(2025/05/16)
[ あわせて読みたい ]
非機器的早期運動療法はDVT発生率を低減【論文から学ぶ看護の新常識】第1回(2025/02/05)
トレンド・トーク『肺がん』(2024/06/11)
災害対策まとめページ(2024/02/05)
Dr.大塚の人生相談(2024/02/26)
IBD(炎症性腸疾患)特集(2023/09/01)
旬をグルメしながらCVIT誌のインパクトファクター獲得を祝福する【Dr.中川の「論文・見聞・いい気分」】第63回(2023/08/29)
エキスパートが教える痛み診療のコツ(2018/10/11)
医療者向け『学校がん教育.com』(2022/12/01)
アトピー性皮膚炎・乾癬特集まとめインデックス(2022/11/11)
アトピー性皮膚炎・乾癬特集まとめインデックス(2022/11/11)
